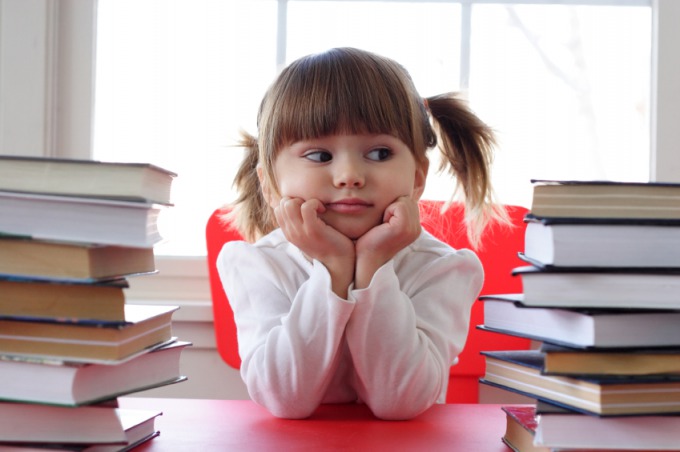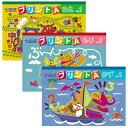妊娠13週に入りました。先週がつわりのピークだったようで、起きている間ずっとムカムカして、ひどい食べづわりなので何かを食べるたびにもう体がはち切れそうになり、かなりしんどかったです。赤ちゃん返り中でママべったりの2歳の娘は一瞬たりとも私が横になることを許してくれないのもまたきついですね…。ちょっとでもゴロンとしようものなら「ママ、おきて~」という厳しい一声が…。すぐに起き上がらないと泣き出すので(何かの訓練!?)、諦めて娘と一緒にお昼寝するようにしています。
「一体これがいつまで続くのだろう?」と思って前回つけていたマタニティダイアリーを確認してみたところ、16週くらいまでは何かしら「気持ち悪い」ってなぐり書きしてありました…。まだまだ続くということですね。せめて軽くなってくれるといいのですが…。
さて、つわりで眠れぬ夜のリサーチですが、最近は知育系や習い事の調べごとにシフトしております。
今回はズバリ「プリント」。2歳の娘でも取り組むことができそうなものに絞って調べているところです。今日はその途中経過をメモ。
そうはいっても、今のところすぐに何かのプリントを始めようと思っているわけではありません。
娘が2歳1か月の今やっていることと言えば、市販のくもんのドリルでシール遊びをしたり、はさみ・のりなどに触れること。それから気が向いたときにちょっとした運筆練習を少しずつやってみるという程度です。時期が来て娘に合いそうな素材が見つかれば、プリントも少しずつやらせてみようかなと思っています。
調べたところ、2歳から始められるプリントや、だいたい2歳半あたりからを目安にしているものなど、2歳の子どもが取り組める教材は思っていたよりもあるみたい。来年の2人目出産時に娘は2歳7か月になっているので、その頃バタバタしないように、年内に見本など出来るだけ取り寄せたりダウンロードしたりして、じっくり検討してみる予定です。
ちなみに娘が2歳半ば~3歳の間に何かしらのプリント学習を始めると仮定して、その前にカードを主体とした教材、2歳半からは数についての教材を別に始めてみる予定です。それから、こどもちゃれんじももう少し続けてみるつもり。そのあたりのことや英語についてはまた別の機会に書きますね。
2歳から始めるプリント教材といえば、夫婦で愛読している大川翔さんの「ザ・ギフティッド」に詳しい記述があります。お母様が幼少期の取り組みについて詳しく書かれた第7章「母さんの解説」を読むと、翔さんが2歳半になったあたりからいろいろなプリント教材への取り組みを始めたそうです。
- 2歳半ごろから「すくすくどんどん」
- 3歳から「公文」(国語と算数)
- 3歳ごろから「七田式プリント教材」幼児用A・B・C全部(Dの途中でカナダへ)
公文について書いてあるところを読むと、プリントに取り組む時間は1日5分~10分と、とても短かったそうですが、絶大な効果があったそうです。翔さんはプリントをたくさんやりたがる子で「もう今日はこれでおしまい。また明日ね」と言わないとやめず、切り上げるのが大変なくらいだったそうです。机に向かってお勉強というよりは、ゲームのような感覚だったのかもしれませんね。
ザ・ギフティッド
9歳までに地頭を鍛える! 37の秘訣
翔さんのお母様の著書。幼少期の絵本の読み聞かせや、家庭内でのゲームや遊びなどの取り組みについて詳しく書かれています。(プリント教材については七田式についてほんのちょこっとだけ記述があるのみで、こちらには書かれていません。)
2歳から始められるプリント教材、いろいろ。
2歳から取り組めそうなプリントについて、メモしてみます。いくつか資料請求をしてみたので、改めてまた記事にしようと思います。
すくすくどんどん
Mashaは「ザ・ギフティッド」を読んでこの「すくすくどんどん」という教材のことを初めて知りました。翔さんのお母様は、このプリントをはじめたことで「親のふだんの手抜きをマザマザと反省されられた」そうです。出てくる言葉のレベルがかなり高いとか。
いろいろな本を読んであげたり、あちこちへ連れて行ってさまざまなものを見せたり、話しかけたりしてきたつもりだったものの、「甘かった!」と思うことしばしば。「そういえば、この言葉、使ったことなかったなあ。これ、見せたこと一度もないなあ。盲点を突かれたなあ」と感心させられる言葉がたくさん出てきました。
そのため我が家では、この教材で勉強するという意識ではなく、むしろ、どういう分野のどういう言葉をまだ知らないのかを、「親が発見する」ために利用しました。
翔が知らなかった言葉は、紙の上で教えるだけでなく、後日、実物を見せるように心がけました。
~「ザ・ギフティッド」より
プリントだけに限った話ではありませんが、「子どもが知らなかった言葉については後日実物を見せるようにする」ということがやはり重要なのでしょうね。
もちろん知っている言葉の理解を深めるためにも、娘にはできるだけ実物を見せる機会を作っていくようにしたいです。
「すくすくどんどん」は、お受験でも使えるなかなか手応えのある教材だそうです
HPを見てみると、ラインナップがかなり少しわかりにくいのですが、2歳から始めるならすくすくどんどんの最年少版ということになるのかな。
製本版、電子版プリント最年少、そして電子版を印刷したものから選ぶことができます。このあたりはもう少し整理して追記します。
電子版プリントが気になっています。
公文
プリントといえば公文のイメージが強いMashaですが、2歳の幼児でも教室に通うことは可能ですし、市販のドリルを購入して進めていくというやり方も可能です。
いずれ娘を公文の教室に通わせてみることも検討していますが、当面は市販のドリルやカードを上手に利用していきたいと考えています。
くもんの はじめてのおけいこ (幼児ドリル)
はじめてのひらがな1集 (もじ・ことば 1)
はじめてのすうじ (かず・けいさん 1)
はじめてのアルファベット (えいご 1)
娘が一番気に入っているのがこちらのドリル。
はじめてのはさみ (こうさく 1)
はじめてのめいろ1集 (めいろ 1)
七田式プリント A~D
「ザ・ギフティッド」の翔さんのお母様によると、七田式プリント教材の幼児用A・B・Cは市販のものと切り口がちがう上、よく工夫されていて面白い教材とのこと。短時間でできる内容のわりに、見落としがちなポイントをついているので、利用して良かったと思ったそうです。(Dの途中で一家でカナダへ。)
娘が始めるとしたら、2歳半が目安になっているプリントAということになるでしょうか。
プリントAを入手するには、同時に「夢そだて友の会」に入会する必要があるようです。
七田式は市販のドリルもたくさん出ていますね。
がんばる舎「すてっぷ」
2歳から始められるようになっています。毎月の教材は、付録もカラフルなイラストもなしで、A4サイズの問題プリントと同サイズで解き方のポイントを記入した解答プリントだけというシンプルな設定。幼児コースは毎月680円なので気軽に始められそうですね。
いちぶんのいち
がんばる舎と同じようなコース・価格設定がされています。幼児年少プリントは1か月615円。ちなみにこちらはカラーだそうです。
いちぶんのいちホームページ 幼児・小学生・中学生の通信教育・家庭学習教材 幼児版
幼児ポピー「ぽぴっこ ももちゃん」
月間ポピーの幼児版。2歳から始められる「ももちゃん」は1か月980円。
こちらのサイトから見本を請求することができます。
アウレラ・メソッド
他のプリントと違って、内容的にお受験を見据えている感が強い印象を受けました。特典も面接の練習などお受験前提のようなものがいくつかあるので、2歳の今だと上手に利用できないような気がしました。季節のプリントや折り紙などの教材はなかなか良さそう。
2歳~年長児を対象に小学校受験・長期的学習に強い【アウレア・メソッド】
「年少」「年中」から始められるプリント教材もメモ。
Z会 年少コース
Z会も幼児用の教材を出していたのですね。いずれ検討してみようかな。
資料請求もできるようです。
くわしい案内はこちらから。
ぷち・ドラゼミ プレコース
ドラゼミにも幼児向けの教材ぷち・ドラゼミがあるようです。
教材がいろいろありますね。
ハローキティ・ゼミ
わが家が最近興味を持っている「こぐま会」とハローキティがコラボした教材。
教材「りんごのえほん」の10ページ(約半分)のダウンロードが可能な無料プランと教材がすべて郵送される有料プランがあります。今のところ年中・年長コースのみ。来年年少コースができたらお試ししてみたいです。
幼児・小学生の通信教育 ハローキティ・ゼミ 教材提供こぐま会
▼こぐま会代表・久野さんの書籍。家庭で出来る取り組みがたくさん書いてあって、とても参考になります。
子どもが賢くなる75の方法
読み・書き・計算はまだ早い!子どもを机に向かわせる前に実際の物に触れ、考えることで差がつく!小学校受験で実績の高い名門幼児教室「こぐま会」の代表が、家庭でできる教育法を一挙公開!
無料でプリントをダウンロードできるサイトをメモ。
無料でプリントをダウンロードできるサイトもたくさんあるようなので、いくつかメモ。まずはこちらで気になる素材をダウンロードして試してみるのも良さそうです。
▼「子育てコラム」も参考になります。
※知育 関連記事